俺、行動力ないんだよね...
こんなことを言われたお盆休み。そんな”たに”の様子を見た僕は「それは違うんじゃない?」と感じます。
行動力の有無は「性格やポテンシャルではなく不安を解消する力が不足してること」が原因だと思うからです。
その人の意思が弱いわけでも、怠けているわけでもないと思います。
ただひたすらに、不安が行動のブレーキをかけている状態。だから不安を解消する力を鍛えれば行動力は自ずとついてくると考えています。
今回は、『不安の正体とそれを解消する力=行動力』についてお伝えします。読んだ後には、行動力がある人は特別だ。なんて思いはきっとなくなっているでしょう。
それではスタート!
行動できないのは性格のせいじゃない
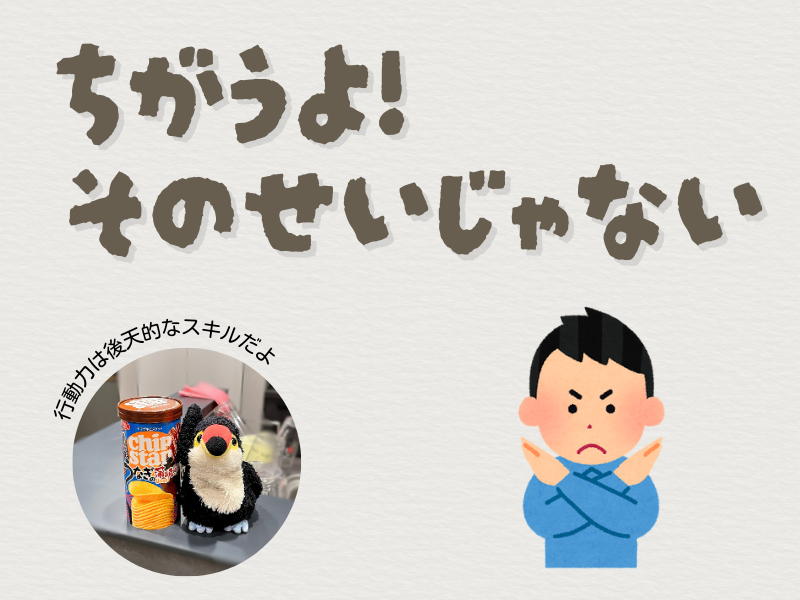
行動力は生まれつきではなく”スキル”
『行動力がある人』という言葉を用いたYouTubeやSNSでの発信を見ると疑問を抱くことがあります。それは行動力の差ではなく、不安を認識して解消する力の差だと思うからです。
人は自分の心を守るために、気づかぬうちに不安を感じてしまう生き物。それは心を守るための大切な機能だということは置いといて、その不安を解消できるかどうかが大切です。つまり、スキルの観点から考えるが良さそうです。
やる気がないからじゃない、という事実
行動力があると言われるねぐちvsたにを比較すると、とても分かりやすいです。
- 【ねぐち】不安を感じたとしてもその度に「すぐに解消に取り掛かる」タイプ
- 【たに】不安を感じたらやらないことで「不安感を薄める」タイプ
このふたりを比べると、やる気があるかどうかの影響はあまりないことが分かります。自分の抱いた不安をどう扱うかが大きな鍵です。
ほとんどの人は”不安”で足が止まっている
さらに、不安を感じてることに気づいていない人も多いように思います。だから、そもそも不安を解消しようという方向に働きかけないのだと思います。
結果として、いつまでも動き出そうという心の状態になることはなく行動できないまま時間が過ぎていく。そんな流れになっている人をよく見かけます。
不安を自覚すること、それを認めること、それを解消すること。
この流れに乗ることで行動力がついてくるはず。最初は大変ですが、丁寧に理解していけば光は見えてきます。
行動力という漠然とした広い言葉を使うのではなく、もっと細かく・具体的な言葉にすれば”たに”も行動できるはず!
説明、お願いします!
不安が行動を止めるメカニズム
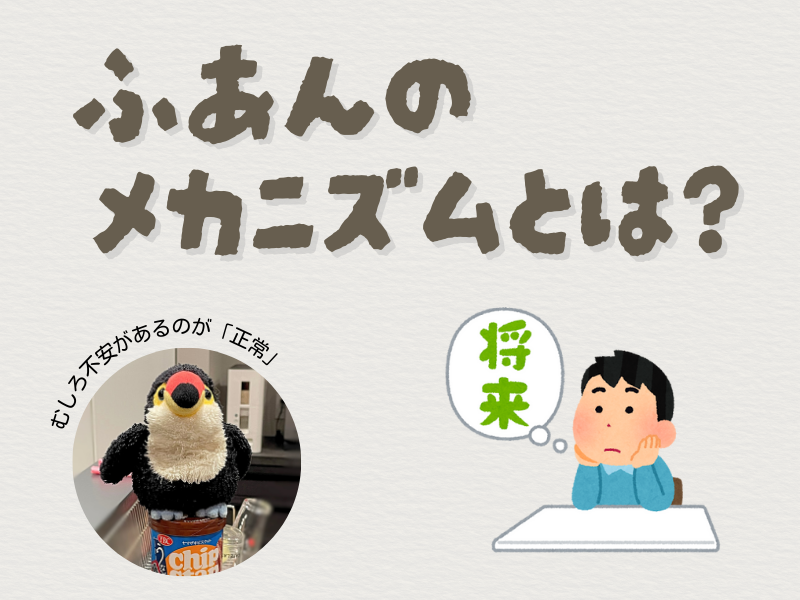
脳はリスク回避を優先する仕組み
人間の脳は将来的に自分に起こる可能性のあるリスクを回避しようとする力が働きます。そのため、人は不安を感じるのです。
そういった脳の特性が備わっていることを知っておくことが大事。
- 不安というのは将来・未来のことに対して感じるもの
- 「どうなるかな?」「大丈夫かな?」という先への不安を感じているんだ
- 自分の脳は正常に機能してるんだ
こういった知識を知りながら捉え方を柔軟にしていくことから始めましょう。
不安を感じること自体が悪いのではなく、リスク回避のために不安を感じるものなんだという仕組みを知っておきましょう。
やらない方が安全という誤作動
絶対に失敗したくないから、そもそも挑戦しなければいいとも思っちゃうんだよね。
それだと何も行動できない人になっちゃうよ!
行動すると『失敗か成功か』など、必ず何かしらの結果が出ます。失敗してしまうことを想定するならそもそもやらないほうが安全でベスト。という結論を出しがちなたにくん。それでは、ずっと何も取り組めない人になるので注意が必要です。
最初から大きな行動(ex.異業種への転職、誰も知らない土地での一人生活など...)を進めているわけではありません。小さな行動(=不安解消)の積み重ねが大きな行動へ変化に変えていけるので、まずは日常に潜んでいる小さな行動の練習を積み重ねることから取り組めば大丈夫。
日常に潜む小さな不安って?

【例①】今日のランチ決め
〇〇のお弁当屋さんのランチ食べたいなぁ〜
でも、店が閉まってたらどうしよう。それだったら嫌な気持ちになるから、そもそも行かないでおこう。
【例②】気になる異性への連絡
〇〇に連絡したいな〜。
でも、返信なかったらどうしよう。それは悲しいから自分から連絡するのはやめよう...
ランチを決める時、誰かに連絡するとき、など小さな不安から取り組むのがベスト。自分が取り組めそうな不安解消からコツコツとやっていくのが個人的なおすすめです。
日常生活の中にたくさん不安は潜んでいるので、その取り扱いに慣れてくれば大きな不安(進学・就職・転職・結婚・出産...など)の取り扱いへの耐性もついてきます。
小さな不安が膨らんでいくプロセス
先ほど例に挙げたような小さな不安をすら取り扱えないとなると、日常生活で常に多くの不安が付きまとうことになります。それでは心が休めることができません。
さらに、結婚や転職、引越しなどの大きな変化に対する不安なんて解消できるはずがないですよね。
人生では、こういった大きな不安を避けることはできません。タイミングや内容は人によりますが必ず訪れます。だから、小さな不安を乗り越えることから取り組んでいきましょう。
それなら俺でも出来そう...!
ちょっとした行動からだな。
不安解消力=行動力の正体

不安を0にしなくても動ける人の思考法
ちなみに、完全に不安がなくなることはありません。リスク回避のために備わっている大切な機能のため「不安ゼロ」の状態になってしまうのもまた問題です。
「不安を抱えたまま解消しない・向き合わない」「不安を一切感じない」など極端な状態しか取れないことが問題なんです。
ある程度の不安を解消できたら、えいっ!と行動してしまうこと。そういったグレーで曖昧な状態を受け入れつつ動いてみようと思えることが「行動力がある人」ならではのメンタルのタフさだと、私は考えます。
準備・情報収集・環境設定で動きやすくする
実際に、不安を減らしていくにはどうしたらいいか?
不安を感じてる対象に対して、準備・情報収集などをすることが効果的です。
- どうやったらうまく行きそうか(ネットやSNS、本などで関連情報を調べてみる)
- 他の人はどうやっているか(上手くいっている人の例を参考にしてみる)
- 自分だったらできそうか?(自分の環境・性格・特性を踏まえて考えてみる)
- 自分がやりやすい環境は?(一人がいいのか・誰かと一緒がいい・教えてもらう・独学?など)
こういった内容と向き合えるようになってくると自然と不安は減っていき、実際に行動に移すことへのハードルは下がっていくでしょう。
完璧ではなく”動ける最低限”を作る
先ほども話したように不安をゼロにしようとすると、終わることがないのでいつまでも動き出せません。だから、最低限のラインを決めておくことをおすすめします。
完璧な準備ではなく、ある程度の準備。
ここまでしたら一旦挑戦してみよう。などと動き出す(行動に移す)基準を先に決めてしまうのが良い手です。
僕の場合は「ちょっとできそうと思ったらOK」ってことにしてます。
そうか、ちょっとでもできそうと思ったらやってみればいいのか〜
不安をほぐす3つのステップ

ここで、今日からすぐに取り組める不安をほぐすための3つのステップをご紹介します。不安を感じやすいタイプだと思う方はぜひ取り組んでみてください。
不安を紙に書き出して見える化
自分が今感じている不安を紙に書き出してみる。これは誰に見られることもないので、とりあえず素直に思うままに書きましょう。
- 新しい職場で人間関係が上手くいかなかったらどうしよう
- プレゼン発表失敗したらどうしよう
- 告白しても振られたらどうしよう
とにかく素直に、ありのままに不安を書き出して自分の目で見ること。そうして初めて、自分はこんな不安を抱えていたんだなと気づくことができるはずです。
「〇〇だったらどうしよう」「〇〇したらダメかな?」など、仮定する際に使用するワード(〜たら、〜れば)は自分の抱いている不安に関連してることが多いです。
自分の抱えている不安が見えるだけでも、少し気持ちに変化があるはずです。
最悪のシナリオを想定して事前対策
新しい職場で人間関係が上手くいかなったという最悪のシナリオを事前にシュミレーションしておくのいいです。実際には、そんなシナリオになることは1割もありません。
ですが、あらかじめ考えておいて対策しておくことでも不安をほぐすことはできます。
最悪のシナリオ(転職Ver.)
- 新しい職場にハラスメントをしてくる人がいた
- しかも一人ではなく会社全体でハラスメントをしてくる(社風が偏っている)と知った
- 自分の要望を伝えたが、話が通じず現状が変わらないまま数年経った
ここまで最悪の展開になることは少ないですし、ここまでなったらその会社は辞めたほうがいいので、もしそんな場面に遭遇したら退職することにします。
一歩だけのスモールステップ行動設計
大きな一歩踏み出そうとするのではなく、まずは小さな一歩を踏み出せる設計からスタート!
転職・結婚・出産など大きな人生の変化の不安を乗り越えるために、日常の不安から乗り越えていく。失敗してもダメージの小さな挑戦はたくさんあります。
行ったことないお店に足を運んでみたり、接点の少ない人とご飯に行ってみたり、ずっとやりたかった楽器に挑戦するでも何でもいいです。
たとえ、それが思ったような結果にならなかったとしてもなんてことありません。
今までの自分よりちょっとだけ勇敢な自分になれたら十分です。その小さな積み重ねが数年後に大きな変化を迎えるときの盾となるでしょう。
【まとめ】行動力は鍛えられる

「行動できない」は不安が強いだけ
今回は行動力の正体とその取り扱いについて説明しました。行動力とは、生まれ持った気質や特性などではなく「後天的に身につけることができるもの」だと思います。
不安の取り扱いが上手な人に備わっている力です。不安を解消する練習さえ積んでいけば行動力は鍛えられます。
不安解消力は人生全体を軽くする「理解は優しさであり武器となる」
どんな人でも、どんな環境で生まれても、どんな生き方をしようとも「人間に備わっているリスク回避の機能(=不安)」が消えることはありません。
不安がなくなってから行動しようと思うのではなく、どうやったら不安を減らせるか?乗りこなせるか?という視点から考えるのが人生を軽く生きるコツ。
僕ねぐちは、よく「のんきだね、お気楽だね」と言われます。それは、何も考えていないわけではありません。
『抱える不安について考えた結果、気にしなくていいことを知った』だけ。ただ、それだけです。
色んなことを理解することができると、自分にも他人にも優しくなります。そして、人生を豊かに生きる上での武器となるんです。
それでは本日は以上です。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました!
